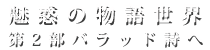第88話 三文文士の慌てふためき
『変装した国王とロビン・フッドの友情』 ("The King's Disguise, and Friendship with Robin Hood", Child 151)
タイトルからして、この作品の内容に現実味は薄いと感じられよう。元々娯楽性の高いロビン・フッド物語であるし、国王が変装するとか、ロビン・フッドに好感をいだくとかいった話は他にもあるわけだから、特にこの作品だけが咎められることでは無い。18世紀頃からロビン・フッド詞華集の出版が盛んになって、多かれ少なかれ、流布していた作品の二番煎じや三番煎じが生まれ、その出来栄えには玉石混交があった。今回紹介する作品においては、最後の最後で不出来ぶりが暴露されるということが面白い。チャイルド収録のロビンフッド・バラッドの様々な側面を紹介しておくことが筆者の狙いである。
イングランド王リチャードI世(在位、1189-99)がロビン・フッド一味の悪戯を耳にすると「彼らの所業をいたく気に入り/ぜひとも会ってみたい」と思って、12人の家来を伴ってはるばるノッティンガムにやってくる。しばらくそこに滞在し、ロビンとの面会を交渉するが、話は一向に進まない。そこで、修道士に変装して、ロビン一味が待ち伏せるバーンズデイルに出かけてゆく。出会ったロビンは「不倶戴天の敵/大修道院長(アボット)」だと思い、チャンス到来と喜ぶのであった。王の馬の頭を掴んで、「止まれ 大修道院長(アボット)/おまえのような贅沢者は/一度 痛めつけねばならぬ」と言うと、王みずからが応えて、「我らは王様の使者であるぞ/王様はそなたと話をするため/この近辺でお待ちである」と言う。ロビンが、「王様に恵みあれ・・・/王様を愛する者たちにも恵みあれ」と言うと、王は、「そなたこそが冒涜者ではないか/裏切りを働いたのではなかったか」と問い詰め、ロビンは、「俺が心から憎むのは/税金を食い物にする悪党ども/・・・/憎むべきは聖職者たち/近頃 権力を振う者たち/売女(おんな)を侍(はべ)らせる修道士と托鉢修道士/そんな奴らから金を奪うのだ」と、己の行動の正当性を主張した上で、一行を緑の森で歓待しようと申し出る。ロビンの角笛に集まった110人の仲間たちがお頭の前にやって来て順々にひざまずく光景を目撃したリチャード王は、「なんて 勇壮な光景だ」と感激する。王は内心で、「ロビン・フッドの一団は/我が廷臣よりも慎ましい/宮廷人も森から学ぶべき」と呟く。晩餐の席では、王も初めてだと言うほどの歓待を受ける。酒がまわって上機嫌になったロビンは、「命尽きるまで ワインを飲もう/緑の森に住む限り」と言い、「王様の御前でするように/弓試合を披露しよう」と仲間の者たちに呼びかける。彼らの見事な弓術に感服したリチャード王は、「ロビン・フッドよ・・・/失礼なことを尋ねるが/王に誠意を尽くして仕えると/そなたは心から誓えるか」と訊くのであった。「どんなときにも王に仕え/命も捨てる覚悟」と応えたロビンは、「たった一人の聖職者の悪行のため/聖職者嫌いになったこの俺だが/そなたがこんなに親切だから/再び愛せるよう努力しよう」と、悪に対する憎しみをも乗り越えることを誓う。これに感動した王はこれ以上身分を隠すことが出来ず、自分が「至高の君主 リチャード王だ」と名乗り、ロビンの罪を赦すと宣言する。収まらないのは州長官、「あの憎き悪党め/わしと従者を歓待するのに/たった一皿しか出さなかったドケチめ」と喚く。ロビン・フッドは仲間とともにロンドンの宮殿に向かう。ここまでの話の流れは一応問題無いとして、この歌の作者は、「かつて貴族だったロビン・フッドは/ついに宮廷に戻ることができたのです」と続けて、州長官や修道院長など体制側の欺瞞と悪を暴くことにこそ自らのレーゾンデートル(存在理由)があった筈の森の王者にしてアウトローのロビンを完全に体制側の人間に戻してしまったのである。
この作品が『ロビン・フッドの武勲』 ("A Gest of Robyn Hode" Child 117)の第7、8部を、部分部分を省略してまとめ直したものであることはチャイルドの指摘する通りであるが、上に指摘した宮廷人への回帰が『武勲』の方には無いという違いは重要である。
 |
『武勲』自身が(おそらくプロの詩人によって)様々なロビンフッド・バラッドを456スタンザ、1824行にも及ぶ一つの壮大な物語に集大成したものであるが、その終わり方は151番とは大きく違う。ロビンは王様の宮殿で1年少々過ごした後、「かつて俺は凄腕の射手だった/強く そして逞しかった/この国中で/俺に敵(かな)う射手はなかった/ああ/それがどうだこの体たらく/このまま陛下と暮らしていては/哀しみのため死にそうだ」と言って、暇乞いをする。緑の森と140人の屈強な若者たちの元に戻ったロビンは、二度と王の元に戻ることは無かったとうたわれる。
出版年不詳であるが、1753年前後であろうと推測される『ロビン・フッド詞華集』(Robin Hood's Garland)に収められているこの151番の出来具合についてジョーゼフ・リトスンは、「この本を何とか出版せんがために発行元から急き立てられた哀れなお抱え文士による極めて忌むべき行為」と述べている(ESPB, III, 220参照)。リトスンの非難を決定的にした感のあるのは最終44スタンザである。「緑の森に住む間 ロビン・フッドは/悪戯(いたずら)ばかりしたものです/さあ友よ こっちに来て聞きなさい/正直者ロビンの最期の話を」とありながら、この歌ではこのロビンの最期の話は出てこない。リトスン風に邪推すれば、急き立てられた三文文士の慌てふためきぶりが暴露されているということか。『武勲』では、森に戻ったロビンがそのまま22年を過ごした後、最期を迎える事情がうたわれているのである。
ひとくちアカデミック情報:
ジョーゼフ・リトスン: Joseph Ritson (1753-1803). 古書(古物)研究家。1795年にRobin Hood: A Collection of All the Ancient Poems, Songs, and Ballads, now Extant, Relative to that Celebrated English Outlaw: to which are prefixed Historical Anecdotes of His Life 2巻を出版した。これを契機にして、ロビン・フッド伝承が学問的な研究対象として価値あるものと認められるようになったと言われる。シェイクスピアのテキスト編纂をめぐるSamuel Johnson攻撃、Bishop PercyのReliquesにおける加筆修正問題に対する攻撃など、その舌口の激しさと気質が相まって、リトスンの徹底したテキスト純粋主義が自らを精神の崩壊に追い込んでいった。1803年に、部屋に閉じこもって原稿の山に火を放って自殺行動に及び、その後死亡。
*データ管理上の都合により、コメント欄はしばらく非公開にさせていただきます。どうぞご了解くださいませ。